Page2023出展回顧録
〜印刷・出版業界における自動組版の役割を考える〜
「Page」は、印刷技術の最新動向をまとめて知ることができる展示会です。
会場では、多くの企業が自社の製品、サービスをアピールしました。
毎年2月頃に開催されていて、ニューキャストもほぼ毎年「自動組版による課題解決」のコンセプトで出展しました。

今回は、来場者の方から伺った「現状の課題」を踏まえ、「印刷・出版業界における自動組版の役割」について考えていきたいと思います。
まとめ
印刷・出版業界は材料費の高騰や印刷ニーズの減少などに直面しており、AI技術の発展により取り残される可能性がある。そのような状況下で、自動組版が注目されているが、その導入にはコストや様々な変化をどう受け入れられるかが課題となる。しかし、自動組版を取り入れることで再利用可能な高精度な情報を得られることは、従来の「印刷物やWEBを作るだけの仕事」から「データを整理、管理する仕事」への移行を助け、より高品質な顧客サービスを提供できると示唆される。
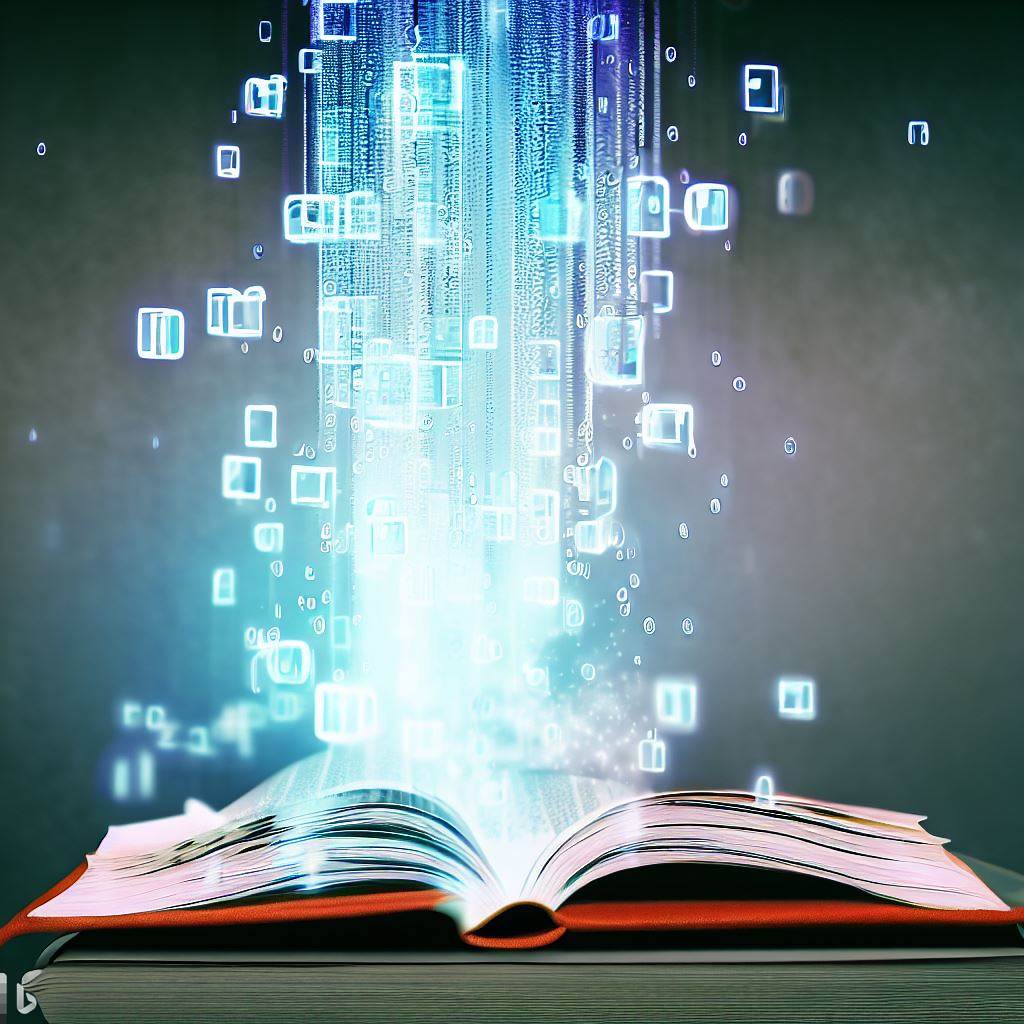
目次
Pageとは
自動組版普及委員会としての共同出展
自動組版の現状と今後
・マニュアル/論文などXMLなどのデータからの自動組版
・カタログやチラシなどの自動組版
・数式や漢文など学参の自動組版
・論文集などの書籍の自動組版
印刷・出版業界における自動組版の役割
Pageとは
(公式サイトはこちら)
主催は印刷技術協会(JAGAT)で、1988年から今年で36回目だそうです。
出展社は、印刷関連の機械・ソフトウェア・サービスを販売・提供している企業。
来場者は、印刷会社、制作会社、デザイン会社、出版社、メーカー、商社、学生です。
最新の技術を駆使した新商品や新しいビジネスの試みなど出展内容は様々で、「印刷業界の現在」をまとめて確認するのに、ちょうど良い展示会となっています。
自動組版普及委員会としての共同出展
今回ニューキャストは、単独出展ではなく、
「自動組版普及委員会(以下ACDC)」として6社で共同出展しました。
ACDC6社は「自動組版」を共通キーワードに活動していますが、それぞれ得意分野が違うので、
ブースに来ていただいた方とのお話しで、
「あー、それはこっちですね」
というように誘導したり、
「これだ」と思って来られた方にも「こんな自動組版もある」だとか
「こういう方法もある」というように、
今までとは違う角度からの課題解決の可能性をお話しすることが出来ました。
実際のところ、来場者が抱える課題は、システムや業務フローを部分的にケアしても解決できないことが多いので、様々な技術や知識を共有して議論する場としての「ACDC」が今後認知されていけばうれしいです。
ACDCの活動としては、Pageのような展示会以外にも、2ヶ月に一度ぐらいのペースで、テーマを決めてセミナーを開催していますので、自動組版に興味のある方は、是非ご参加ください。
自動組版の現状と今後
今回、共同出展に参加したことで、自動組版に対する様々なタイプの来場者の声を聞くことができました。
マニュアル/論文などXMLなどのデータからの自動組版
(得意な企業:サイバーテック・ネクストソリューション・アンテナハウス)
データがすでにXMLである、またはXMLとして必要、という場合には、当然のように自動組版は存在しているので、そこからさらにデータの作成方法や、データ管理、ワークフローなどの視点で質問が多くありました。
自分的には、XML形式に絞ったデータの運用はあまりやらないので、業種業態によっては、特化したシステムやデータの二次利用の需要は、今後ますます増えていくと思います。
カタログやチラシなどの自動組版
(得意な企業:Nジェン・ニューキャスト・アズワン)
主に「DTPを効率化したい」と考えている商業印刷物を手がける制作側の方が来訪され、色々とざっくばらんにお話し出来ました。
予想はしていましたが、現場レベルではまだまだ「自動組版」への取り組みが遅れていると感じました。
一昔前は、向き不向きというのが議論されていましたが、不向きなものは、すでに作業コストが予算に見合わない(=新たな仕組みを導入するコストの捻出が出来ない)という状況にあります。
こういった状況を改善するには、根本的な解決が必要です。従来の考え方では打開策が見えないので、足踏みするしかないのかなという現状が見えました。
数式や漢文など学参の自動組版
学参を網羅して完全対応できるソフトウェアは、いくつかありましたが、モリサワさんのMC系が終了するとのことで、頼みはスーパーデジトリアル(旧EDIAN系)になります。
しかし、価格が高価なこともあり、現状のDTP現場での必要台数の導入は難しいでしょう。
学参なら●●という組版ソフトが無くなってしまったことは残念です。
今は、InDesignに頼るしかありませんが、学参組版のニーズを組み込むとは思えないので、なんとかやりくりするしかありません。
とはいえ、例えば数式を誌面に使いたい場合、TeXやWordのPluginツールなどでは、従来の「見た目」の再現が難しいということと、生産性が低い(手間がかかる)という問題を解決できるソフトウェアを一部利用して、画像としてInDesignに配置するという方法はあります。
ただ、ここでも全て手動でやっていては作業コストが高すぎるので、何かしらの自動組版的考えを取り入れる必要があります。
(そもそも、従来を再現するためのコストが版元から出るのか、という別の問題があることは、ここではしないことにします。)
論文集などの書籍の自動組版
この分野で多かった話は、「原稿はwordでくる、でもDTPに時間がかかっているので自動組版で何とかならないか?」でした。
原稿執筆者が作成したWordデータをDTPに使う場合、現実的には文字ぐらいしか使えません。Wordでいくら頑張って原稿を作ってもらっても、結局のところInDesignに置き換える作業(誌面フォーマット、段落・文字スタイルなど様々な設定)が必要だからです。
Wordで印刷すればいいのでは?と制作会社として元も子もないことを考えてしまいますが、簡易的な書類レベルであればいいですが、書店に並ぶ本、学校、学会などで使う冊子となると、ページ量が多いことと、それらを一般レベルの体裁には統一したいわけです。それをWordで印刷物として完結させるのは、結構面倒で、手間がかかります。時間に対する対価が見合わないので、自分は断ります。
そこでDTPが登場するわけですが、InDesignでやったところで、ちゃんとした作り方(設計やデータの使い方など)でやらないとWordでやるのと大差ありません。
むしろ、原稿や校正のやりとりのところでカオスになる可能性があり、その中で、「間違う」というリスクが発生します。
こういった問題は、Wordなど誰もが自由に使えてしまうツール使っていることに起因しているので、
・markdown書式のようなフォーマットを決めた原稿作りにする。
・オンラインで原稿を書く。
・オンライン上のデータから自動組版する。
で解決します。
しかし、そういったシステム投資に見合う収入があるかというと、今までが作業賃でしか対価を発生させていないので、作業の置き換え、という意味だけでは難しいでしょう。
作業ではなく、データを管理する、整理する。それによって、お互いが将来的に良くなる、という考え方に変えていかなければいけないと思います。
印刷・出版業界における自動組版の役割
今回の展示会で感じたことを書いてきましたが、あまり明るい話はありません。
材料費の高騰や、印刷ニーズの減少など業界にとって良いニュースは聞こえてこないので、今後というと暗いイメージしかありません。
このままでは、ChatGPTや画像生成などのAIが飛躍的に進歩を遠目に見ながら、業界も企業も取り残され、衰退していくしかありません。
こういった現状から「印刷物が商品として売れない」ということで、別の何かのひととつとして「自動組版を検討しよう」と考えて来られた方も多いかと思います。
そういった方々に、
「IllustratorやInDesignでやっている制作作業をDot3を使えば、誰でもクラウド上で印刷用データが作れるんですよ」
「しかもこのデータはWEBや他のシステムに渡して使うことが出来るんですよ」
と説明すると、大抵の方は、その良さは理解していただいたようですが、
現状コスト、今のやり方、見た目との比較を先に考えてしまうようでした。
制作のやり方を変えていくことは、難しい...
見た目が良ければ良い...
ただでさえ苦しい中で、新たな投資はできない...
これらの現実に囚われていると先には進みません。
今私たちが日々一生懸命生み出しているもの、DTPデータやWEBコンテンツのデータはそれ以上何にも繋がりません。
そしてそれは、顧客(もっと大きく言えば社会)とも繋がらないということを意味しています。
そこで、是非やってみて欲しいことがあります。
私たちが日々作り出している印刷物やWEBサイトなどの中を覗いてみてください。
デザインという見た目以外に、情報が詰まっていることが分かります。
特に印刷物の中にある情報は、何回も校正しながら完成した高精度の情報です。
この情報をデータとして蓄積し、再利用可能にすることは、全ての人に恩恵を与えます。
データベースを構築するのはシステムが分かる人達がすること、と思うかもしれませんが、用途や最終的な出力イメージがはっきりしない情報をデータベース化するのは大変で、なかなか完成しません。
しかし、印刷物は結果が目に見えています。カテゴリや情報量、情報の意味、情報の優先順位など、実は私たちは、よく知っているのです。
この高精度の情報を作り出している成果にもっと自信を持つべきです。
この視点にたてば、自然と「作るだけの仕事」から「データを整理、管理する仕事」に移行していきます。
この移行を助けてくれるのが自動組版です。自動組版をするということは、「データを整理、管理」するからです。
このように整理され、管理されたデータは、印刷物やWEBサイトといった見た目として存在する成果物よりも、さらに質の高い顧客サービスへと転嫁できるはずです。

もうひとつ、展示会場での話を最後にしておきます。
まだ業界経験が浅そうな若いデザイナーさんが説明を聞きたいということで、わかってくれるかなぁと思いながらお話ししていたところ、
「なるほど!これを使えば、私たちはデザインの仕事に集中できるってことですね!」
という、自分が言いたかったことを感想としていただきました。
制作業界にもっと若い人材を迎え入れ、クリエイターとしての仕事をして欲しいわけでですが、実際の仕事は、誰でもできるような内容だったり、それを何度も何度もチマチマと繰り返さないといけない現実があります。
わたしたちは、制作とは、面倒であるからこそ成り立つ仕事、ということを慣例として受け入れてしまっているところがあります。
これでは、若い人達は将来を見限って業界を去ってしまいます。
「自動組版」は、面倒で誰でも出来そうな作業をしてくれます。将来有望な人材を「作業者」にせず、「クリエイター」に導く力も持っているのです。

ACDCは定期的にセミナーを開催しています。
参加希望の方には御案内しますのでお知らせ下さい。
- 自動組版 InDesign 効率化 自動化 WPS.3 DTP 生成AIで始める!自分専用InDesignスクリプト入門(その1)
- 自動組版 InDesign 業界 効率化 自動化 WPS.3 DTP 非構造データは構造化できるのか?印刷物のデータ化について
- 自動組版 InDesign 業界 効率化 自動化 WPS.3 DTP 【検証・考察】AI校正の実力と限界、自動組版との関係
- 自動組版 InDesign 業界 効率化 自動化 WPS.3 DTP Web用PDFとは〜page2025セミナー「Web用定期発行プロジェクトの全て」解説シリーズ①
- 自動組版 InDesign 業界 効率化 自動化 WPS.3 DTP 自動組版で業務効率化!校正・修正工程の時間短縮術
- 自動組版 InDesign 業界 効率化 自動化 DTP InDesignが終了したら日本の印刷出版業界どうなるのか?
- 自動組版 InDesign 業界 効率化 自動化 WPS.3 DTP page2025出展とセミナーを終えて〜セミナーで伝えたかったこと
- 自動組版 InDesign 業界 効率化 自動化 WPS.3 DTP page2025セミナー「Web用PDF定期発行プロジェクトの全て」
- 自動組版 InDesign 業界 効率化 自動化 WPS.3 DTP DTPスクリプトセミナーで便利なスクリプトを紹介します
- 自動組版 InDesign 自動化 DTP 「テンプレート」と「パターン」の違いについて〜自動組版のための用語整理
